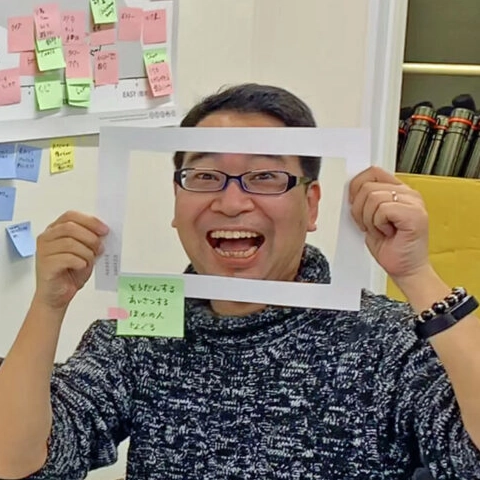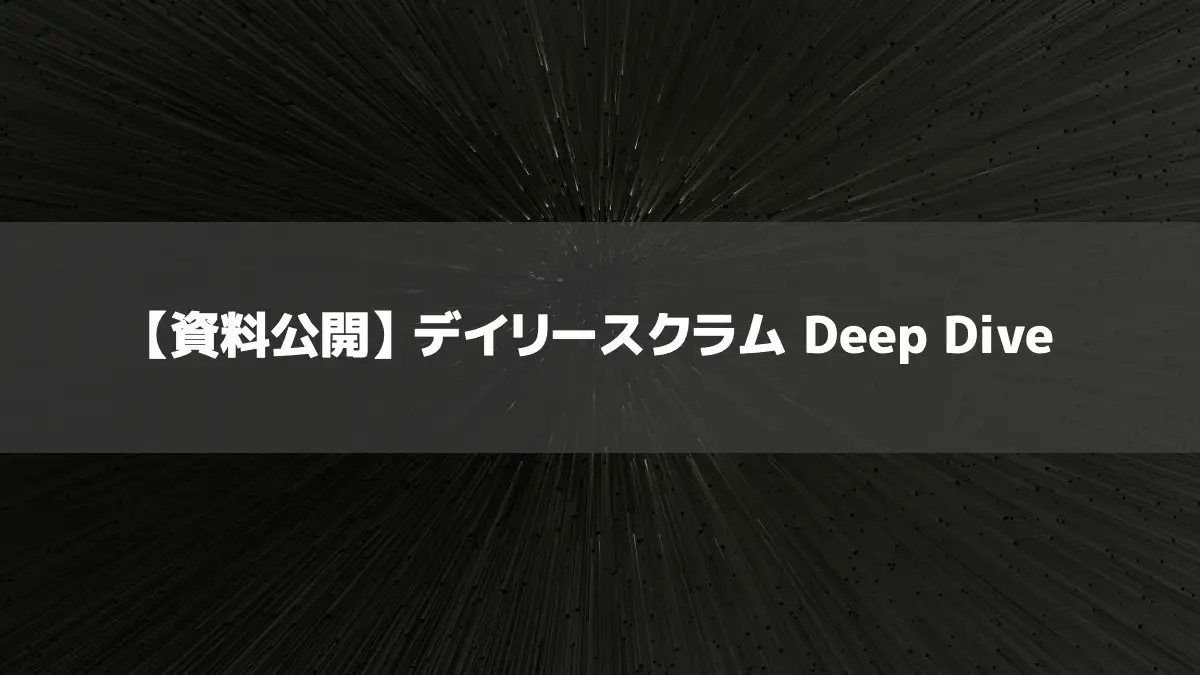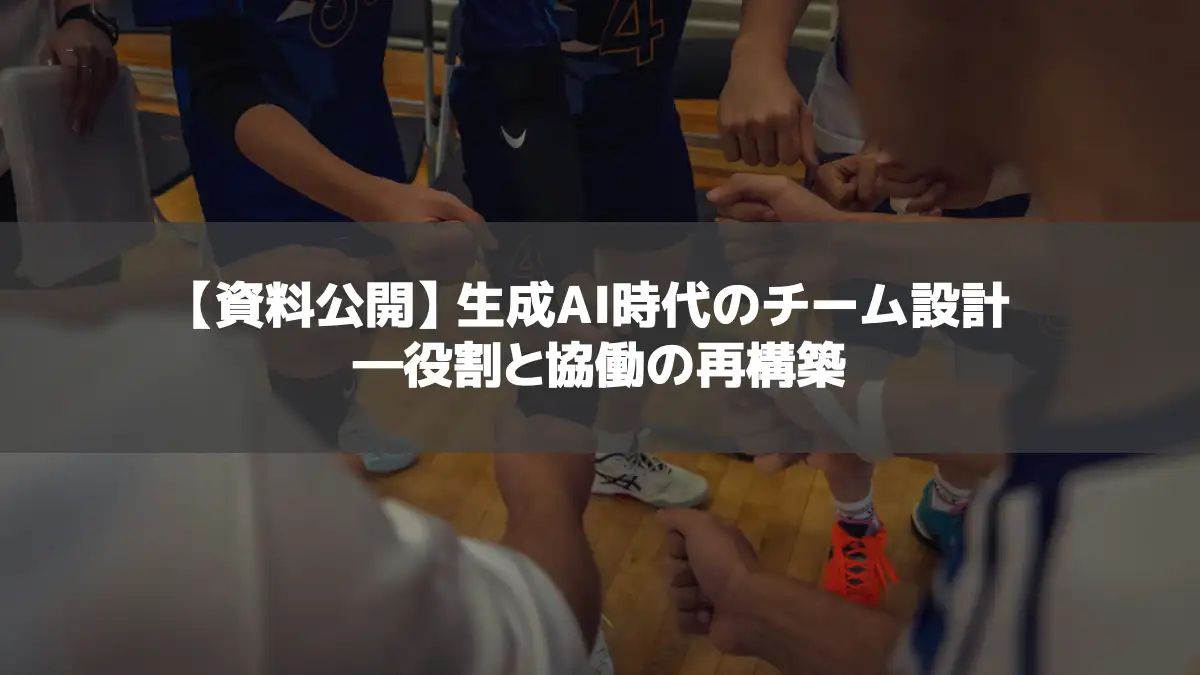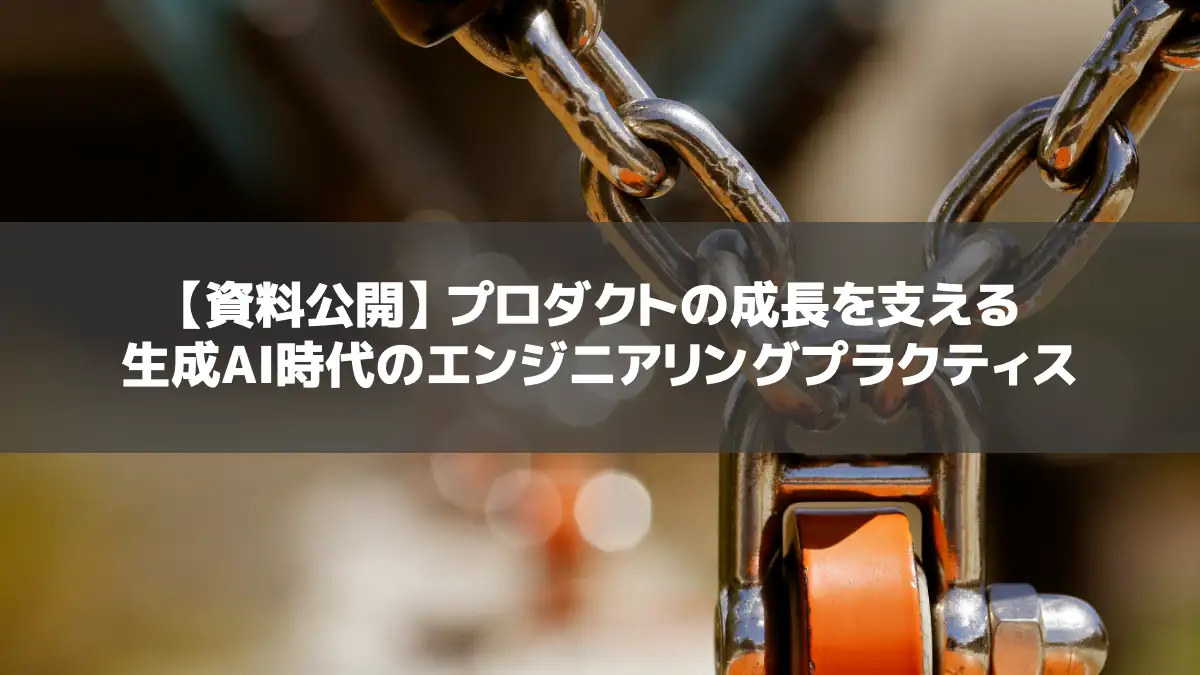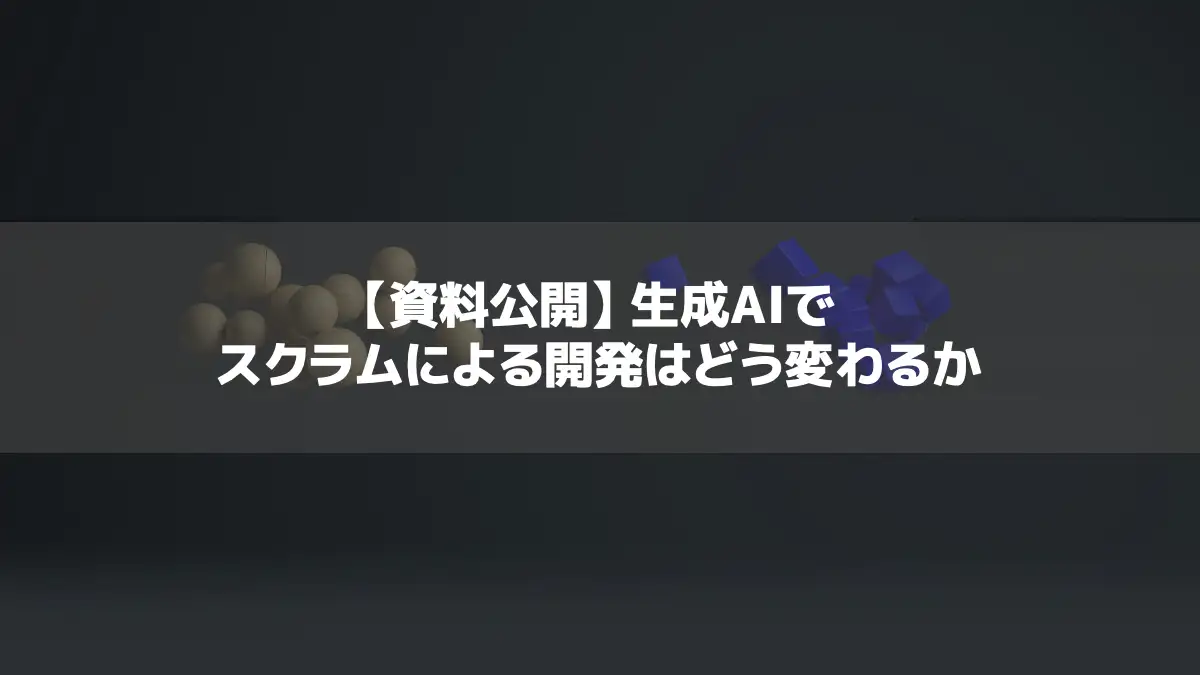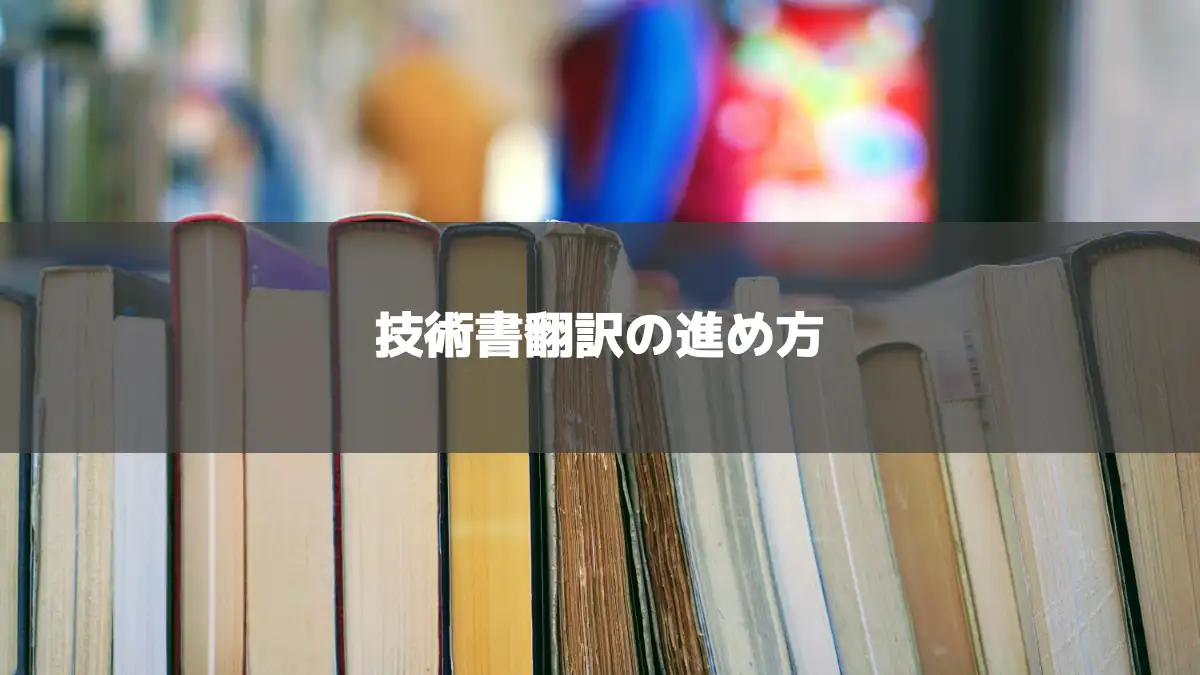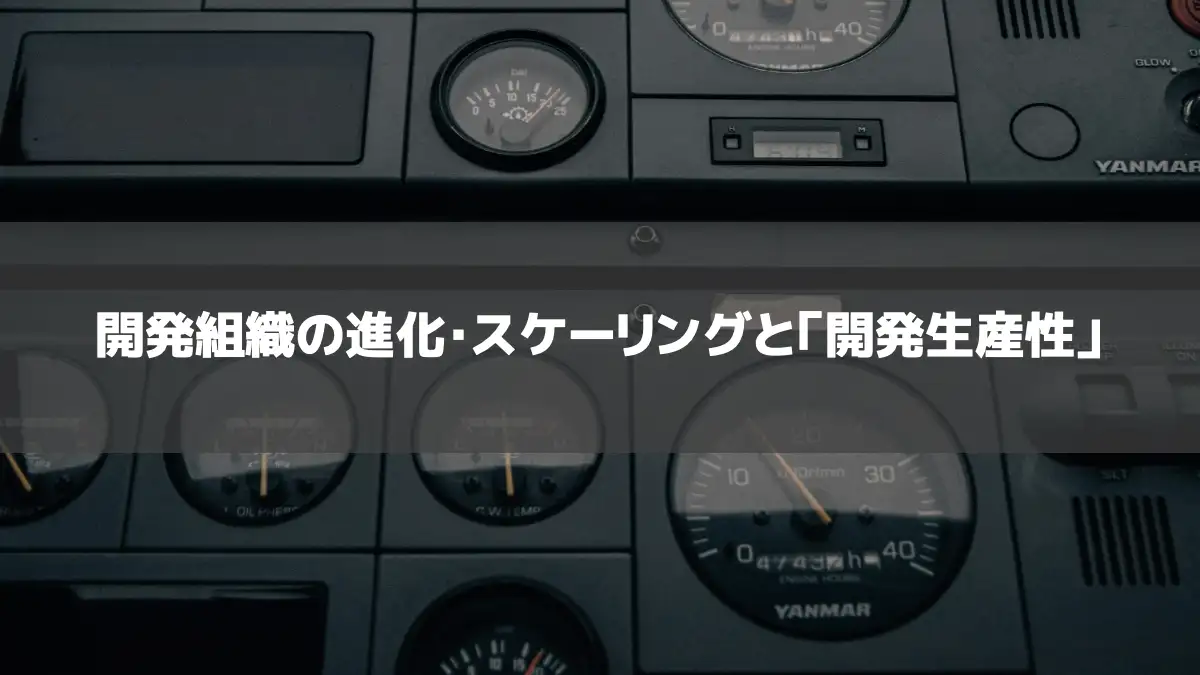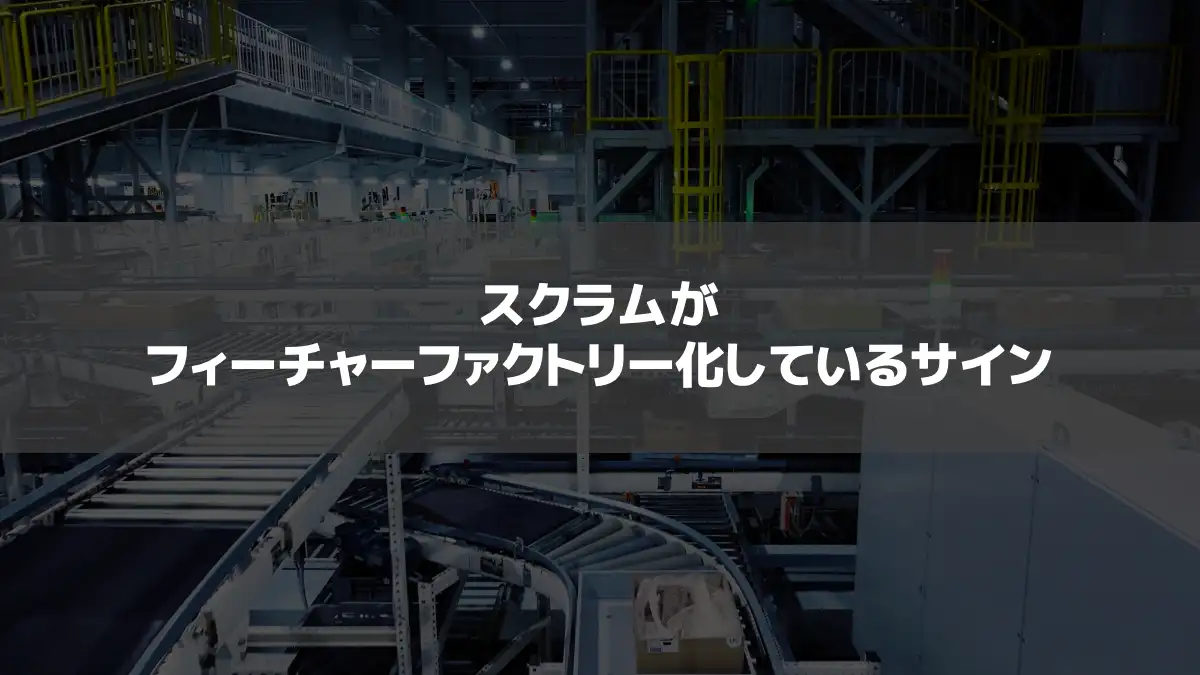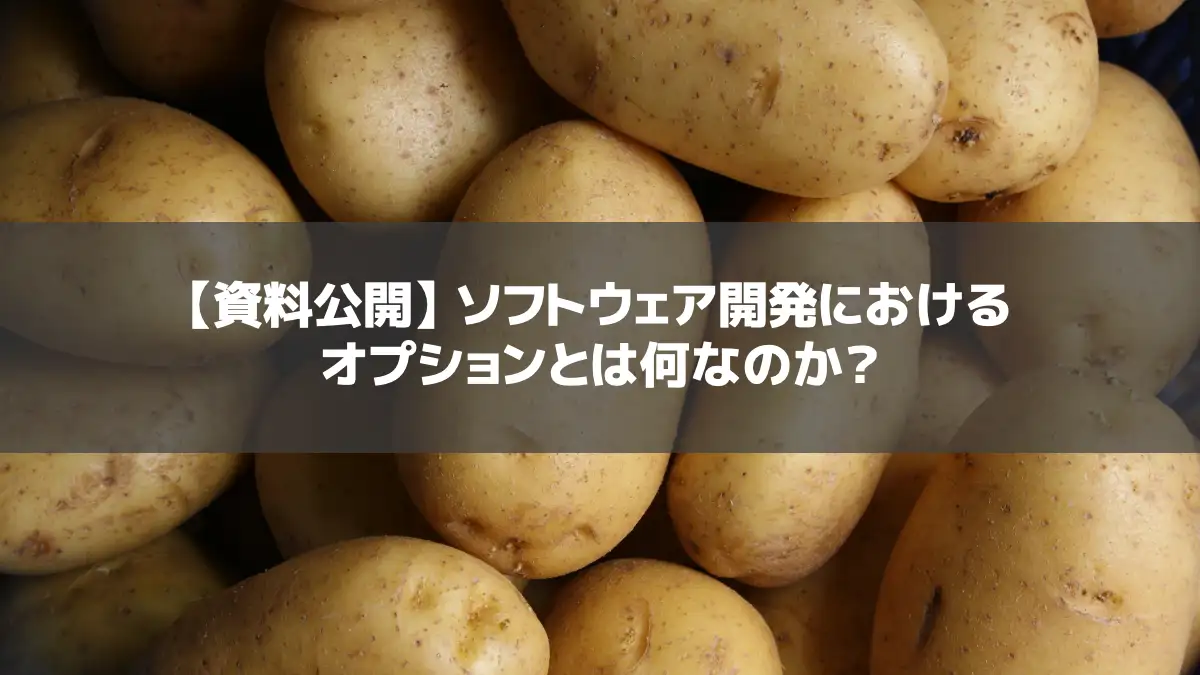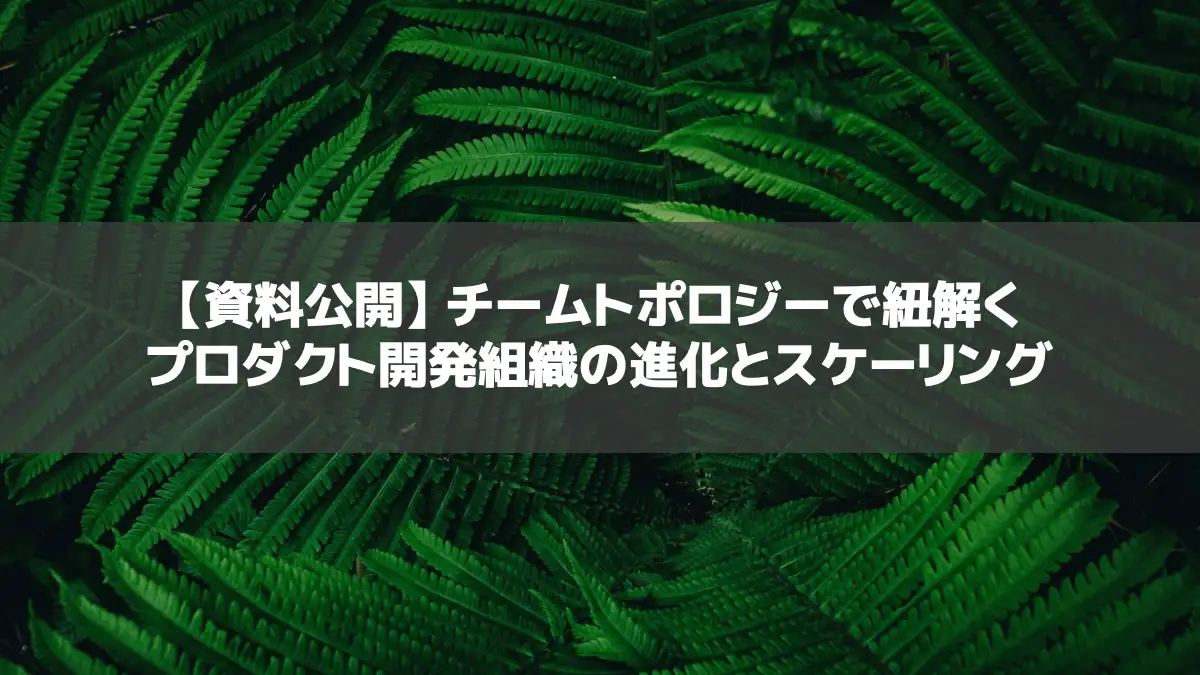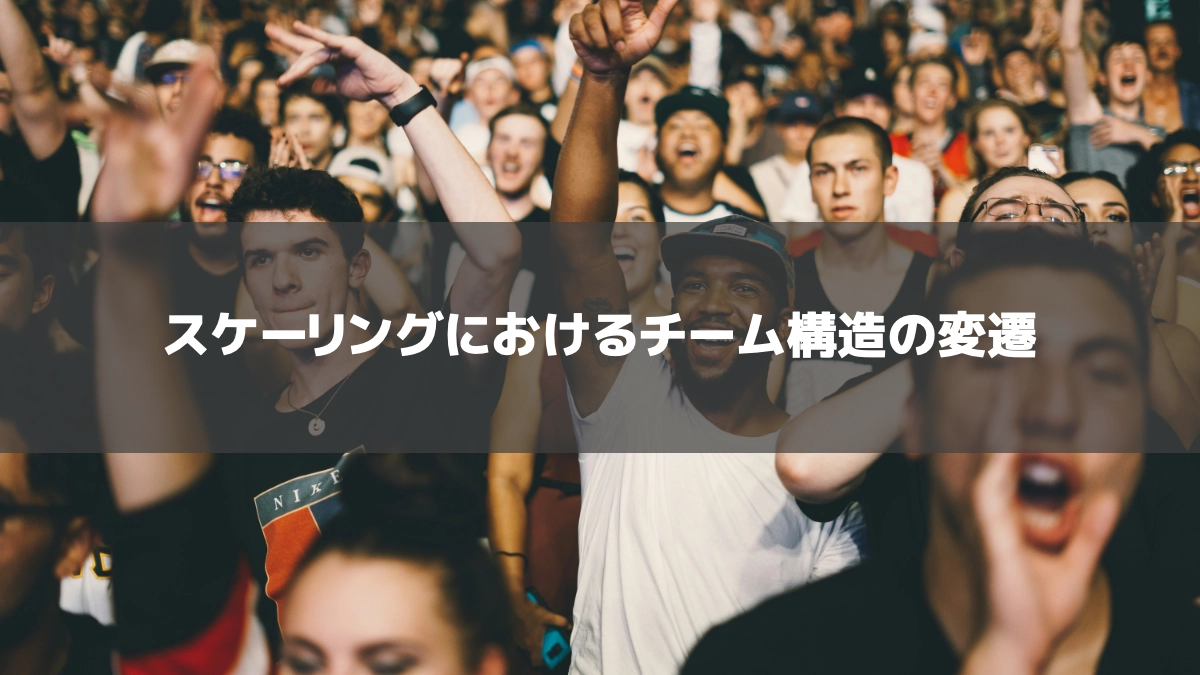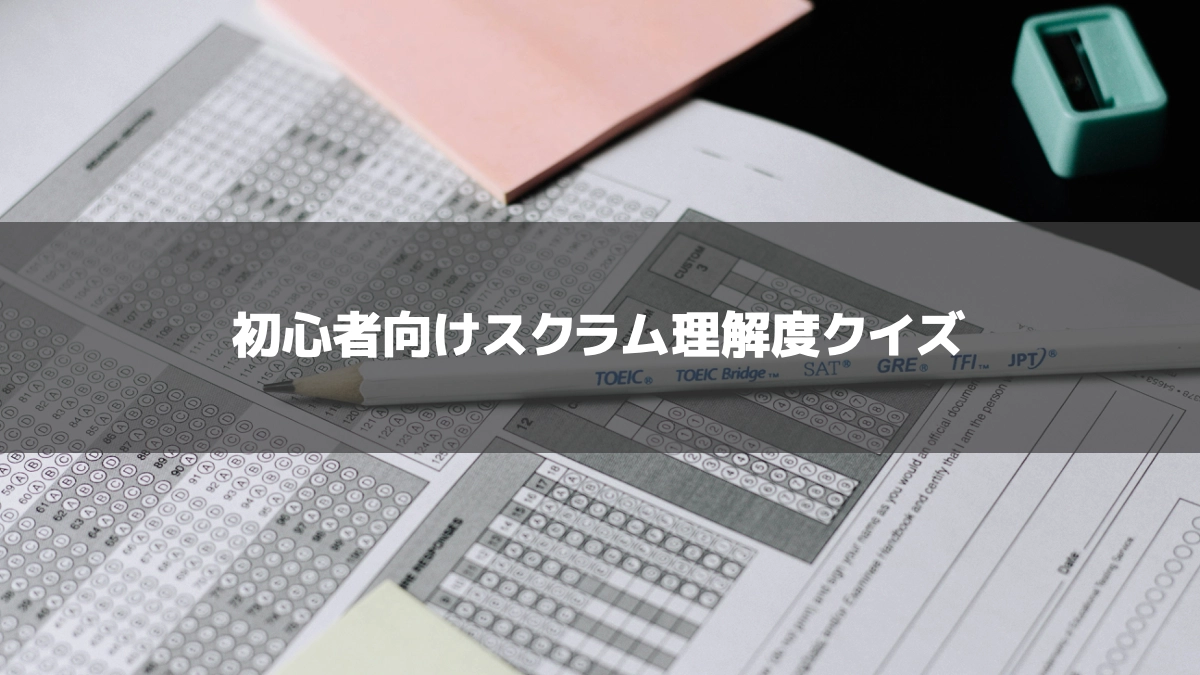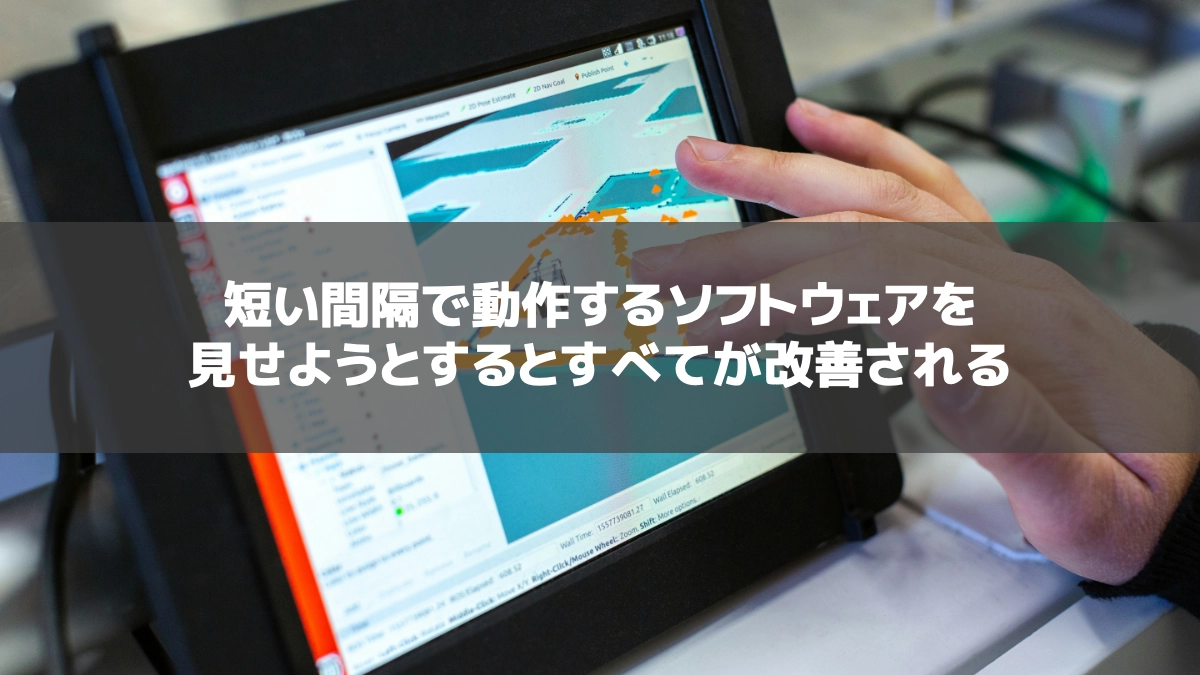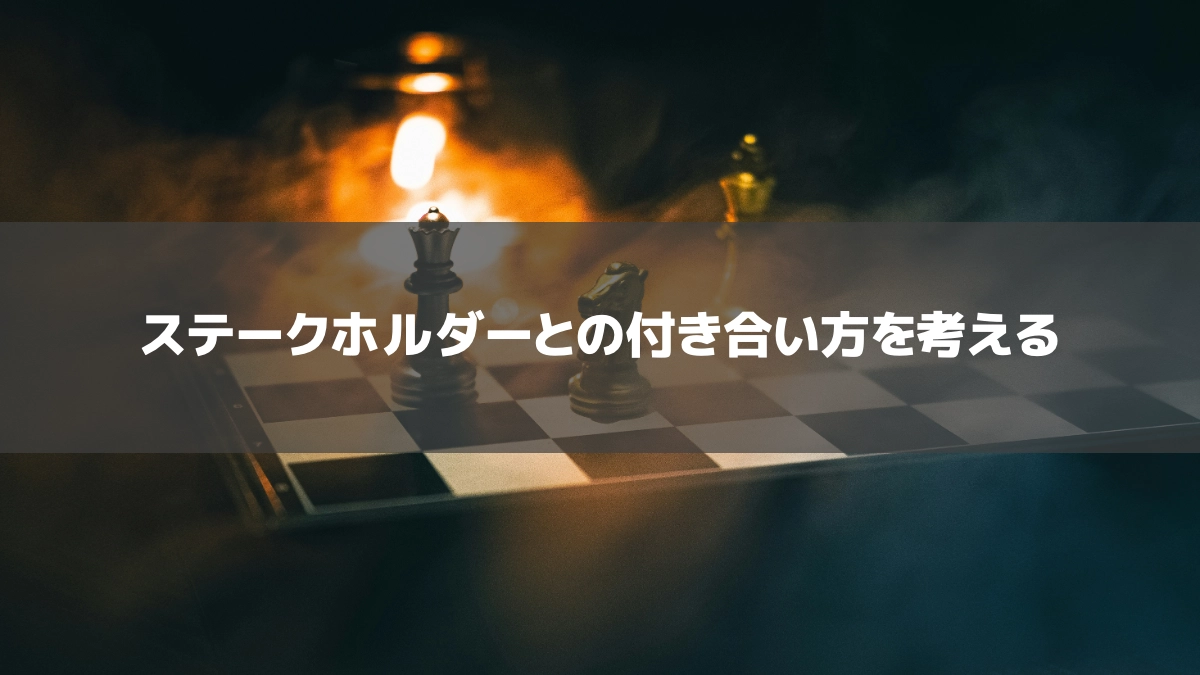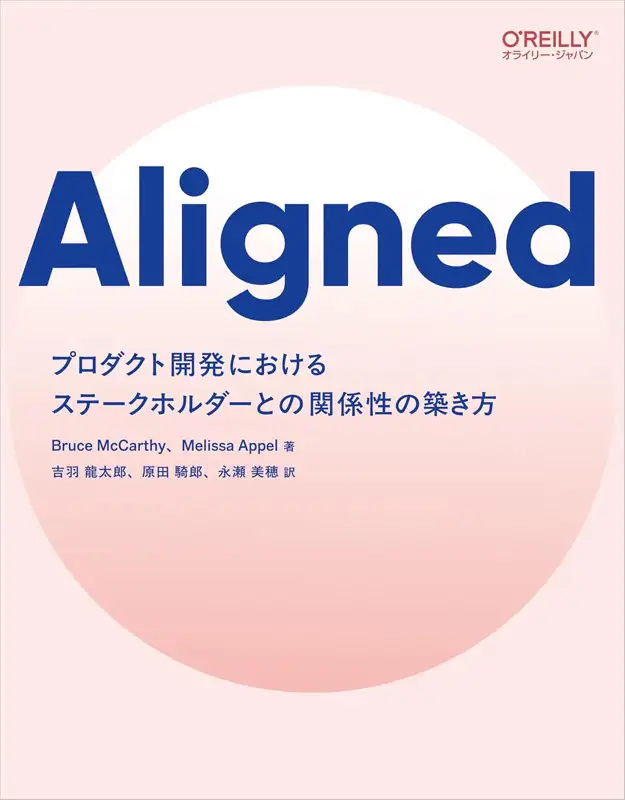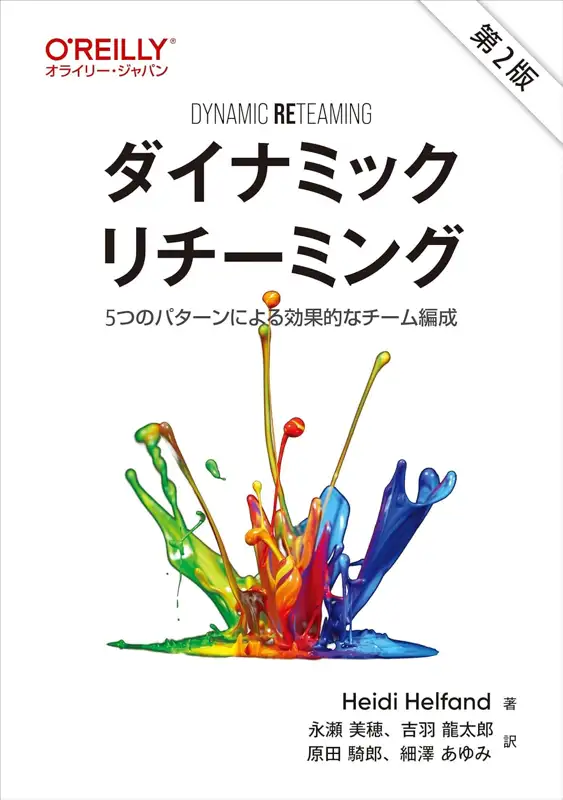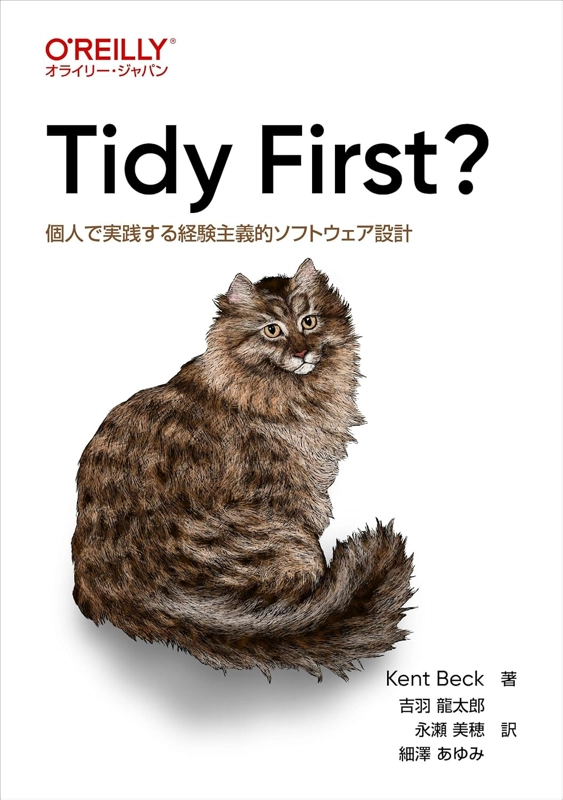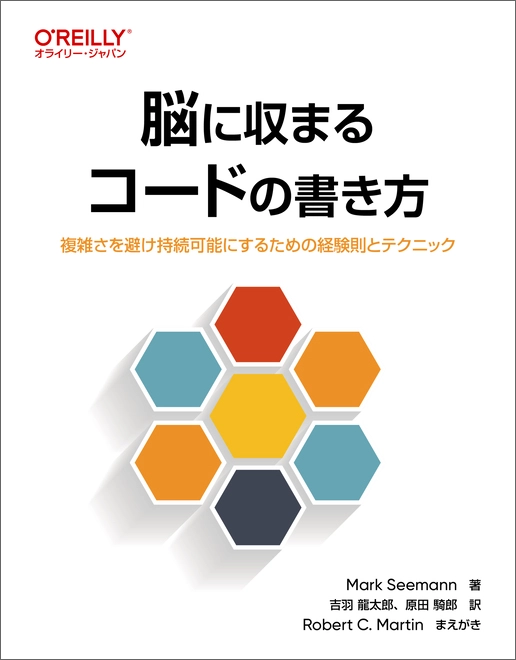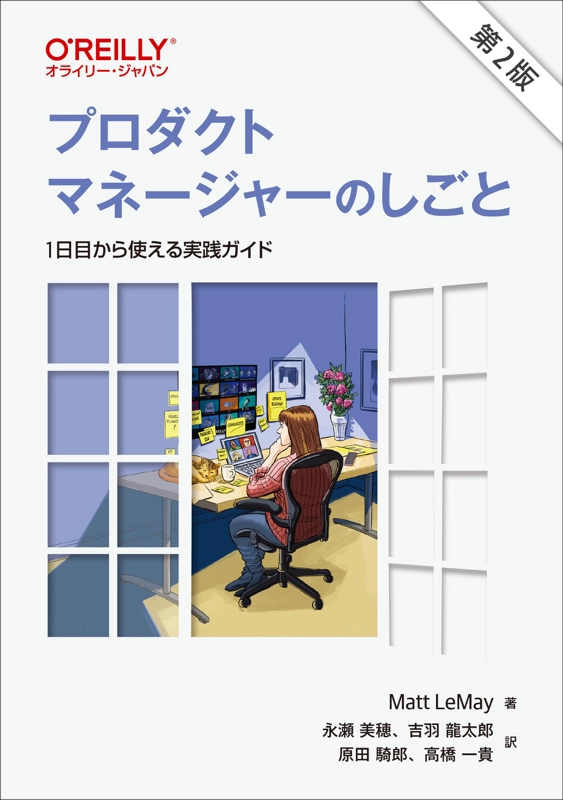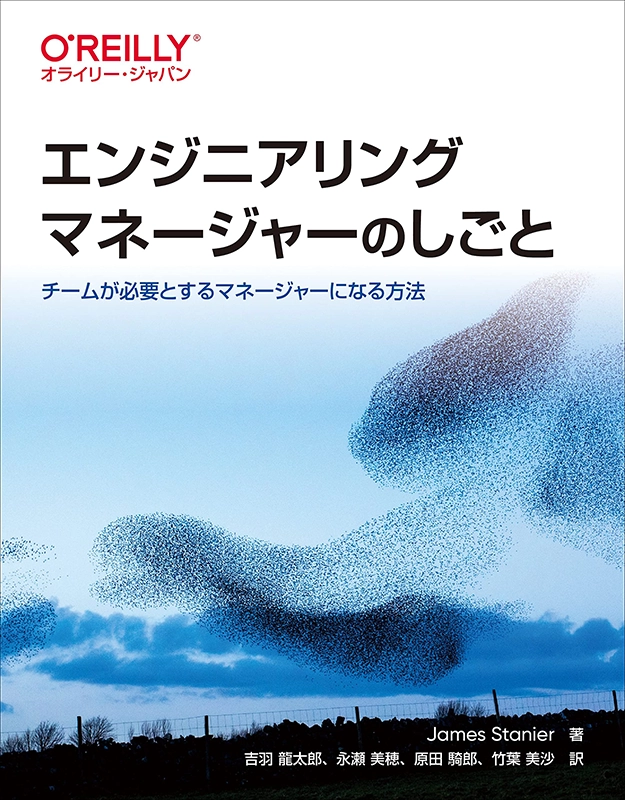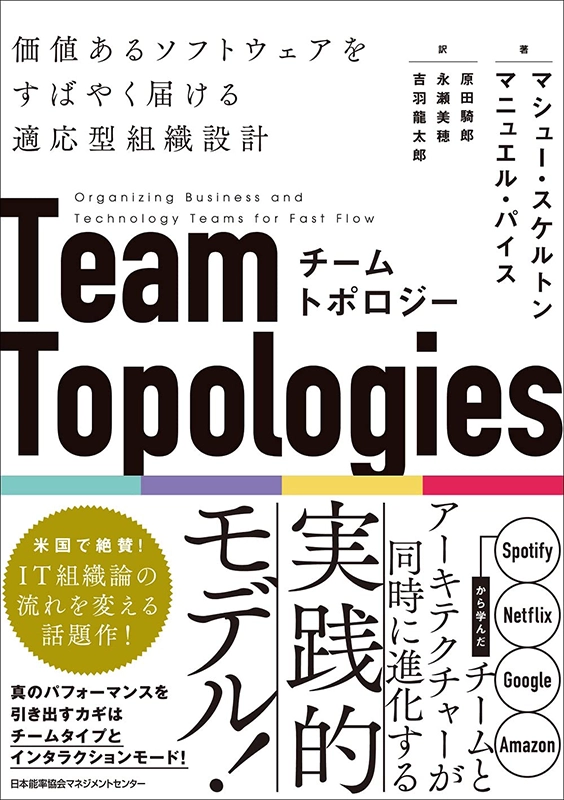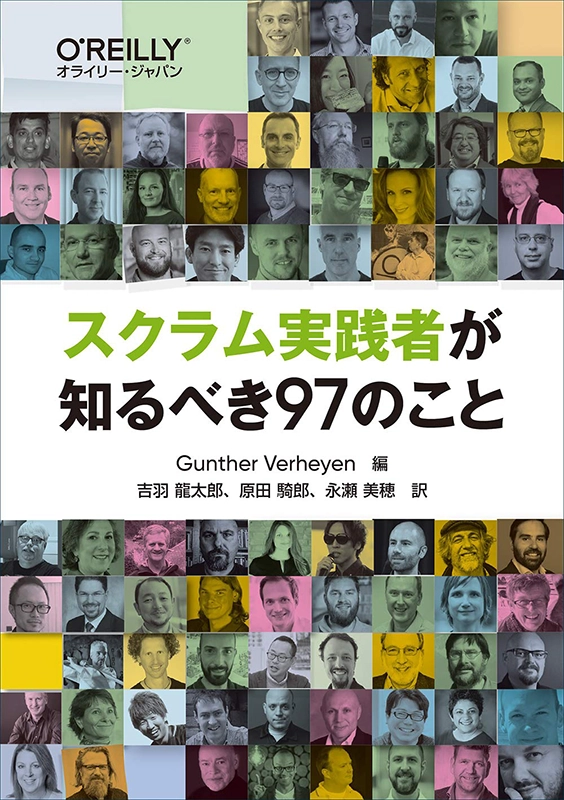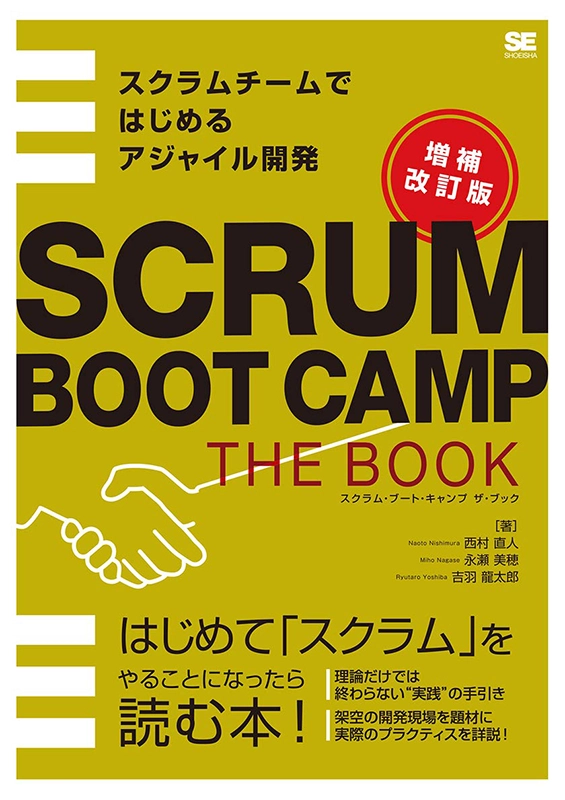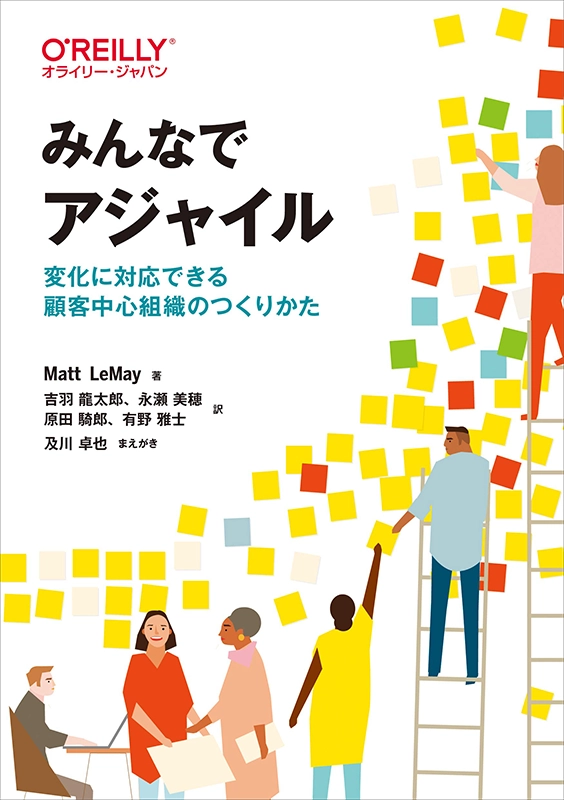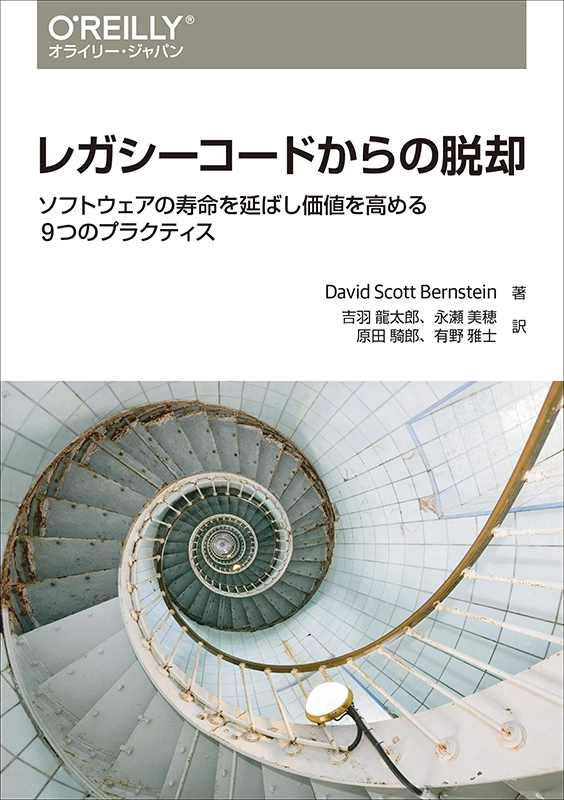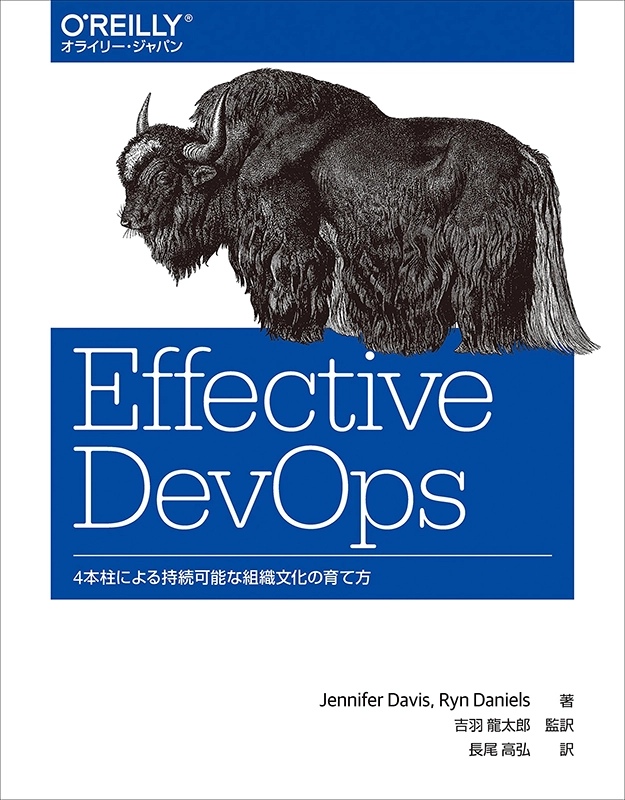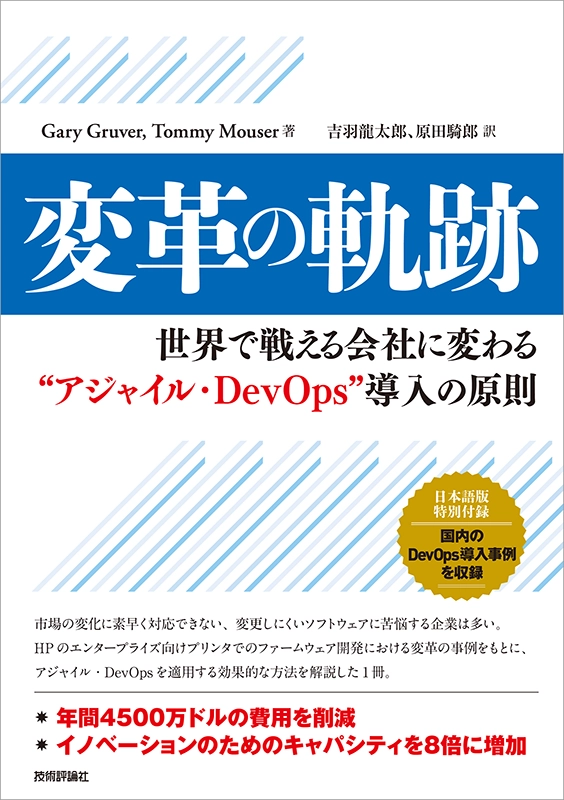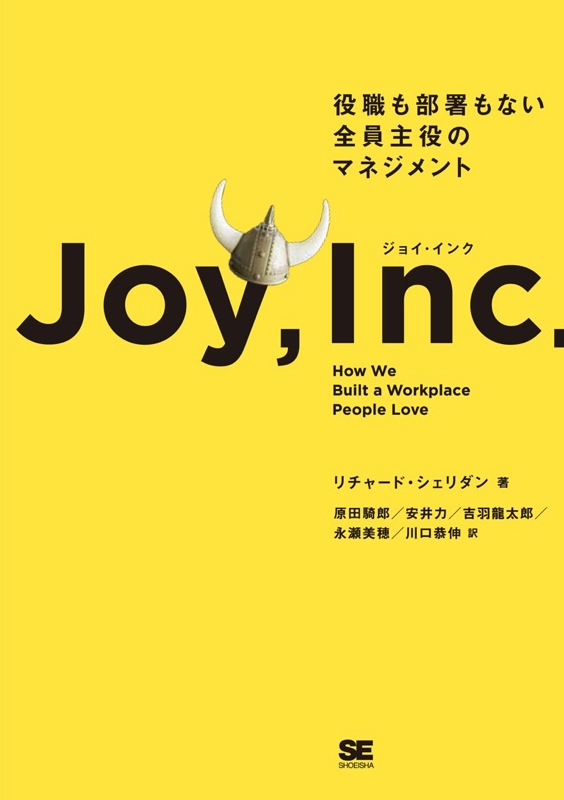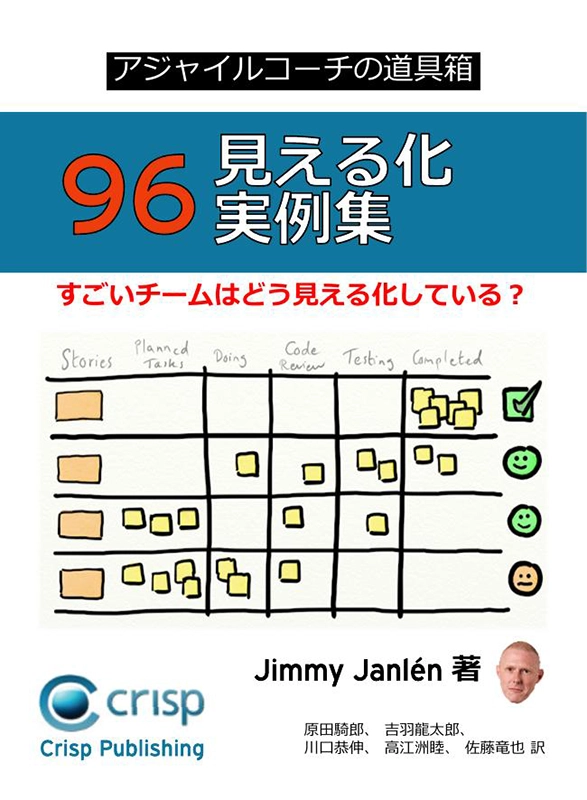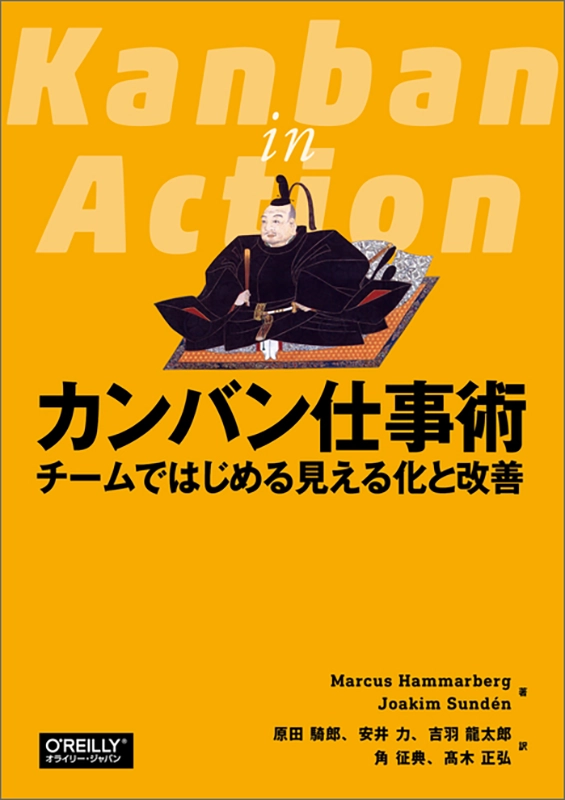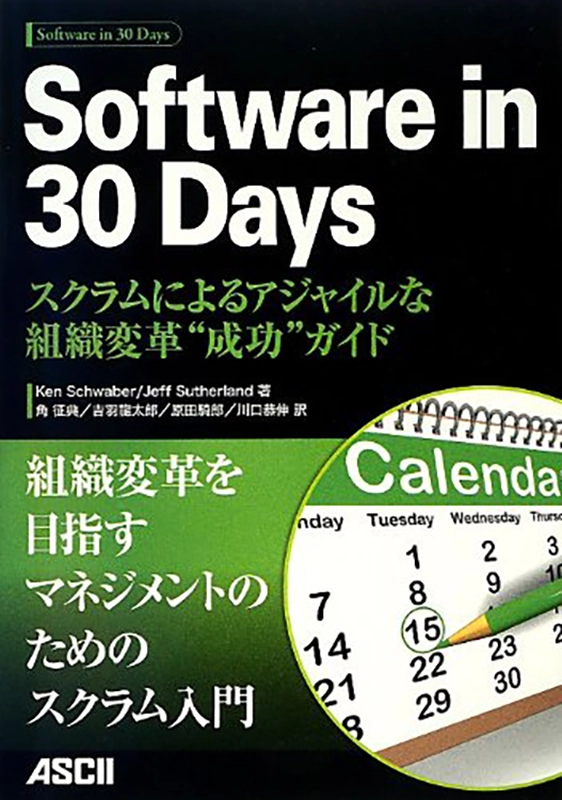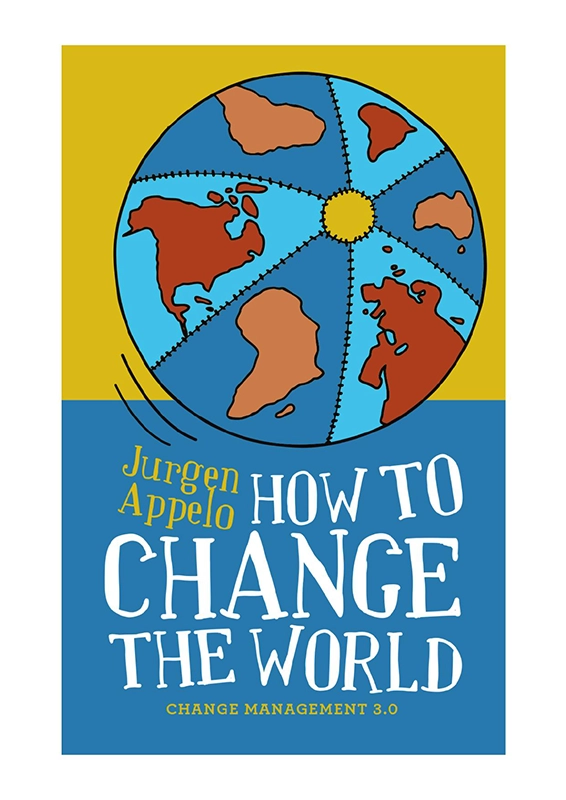直近開催のScrum Alliance認定スクラムマスター研修のご案内
【資料公開】プロダクトの成長を支える生成AI時代のエンジニアリングプラクティス
みなさんこんにちは。@ryuzeeです。
2025年11月14日にお客様先で「プロダクトの成長を支える生成AI時代のエンジニアリングプラクティス」というテーマで登壇した際のスライドを公開します。
なお、タイトルは若干釣りです。
開発作業で生成AIを使うのが当たり前になり、「今後3〜6カ月以内にソフトウェアエンジニアのコードの90%をAIが書くようになり、今後1年以内にはすべての行をAIが書くようになる」とか 「技術スキルのないPdMがVibe Codingで作れた!もうエンジニアはいらない」みたいな主語の大きな話を見かける機会が増えました。 たしかにプロトタイプやモック、検証コードなんかはそのとおりかもしれませんが、成長を始めたプロダクトになるとそうはいきません。
使われるソフトウェアには必ず変更が入るので、変更に耐えられる構造を実現して維持していくことが重要で、そのためには整頓やリファクタリング、設計といった人間の意志の介在が必要です。これはAI時代でも変わりません。 ということで、このセッションでは、整頓とリファクタリングを中心に考え方を整理しました。
参考になれば幸いです。
忙しい方向けのまとめは以下になります。
- 3Xモデル(ケント・ベック)のどの段階かによって、行動原理は異なる
- お金の時間価値と変更可能性というオプションは対立する要素になる
- 整頓やリファクタリングをなくすことはできない
- 使われるソフトウェアにはかならず変更が入る
- 変更の支配的なコストは結合。SOLIDやCLEANで結合を避ける
- AIの出力はアーキテクチャー(設計)に依存する
- その設計力こそがチームの知性の一部であり、投資が必要
- 持続性を確保するためには、AIが出力するコードでも整頓やリファクタリングが必要
- 生成AIによって「実装」は加速したが、「設計」「整頓やリファクタリング」「説明」の重要性はむしろ高まった
- プロダクトの持続性を支えるのは、AIの性能ではなく、チームの知性
それでは。
アジャイル開発チーム向けのコーチングや、技術顧問、Scrum Alliance認定スクラムマスター研修などのトレーニングを提供しています。お気軽にご相談ください(初回相談無料)