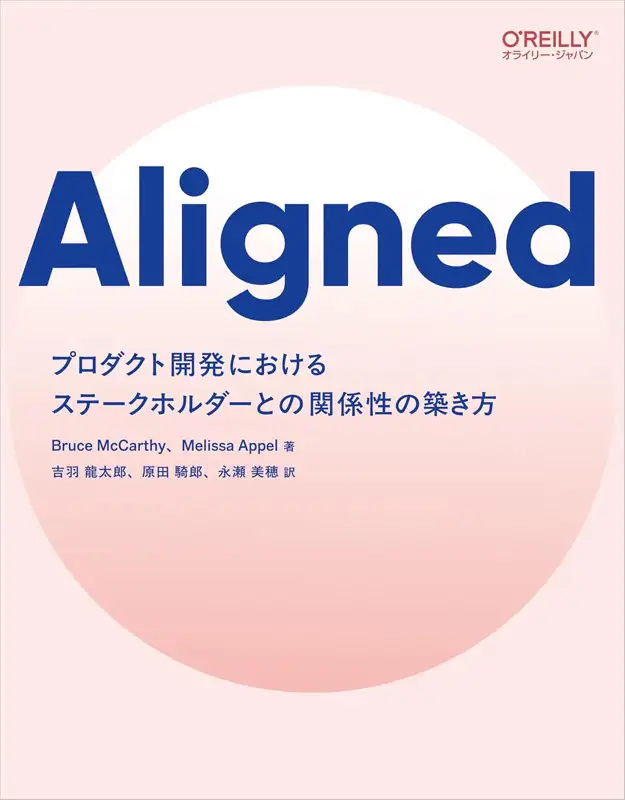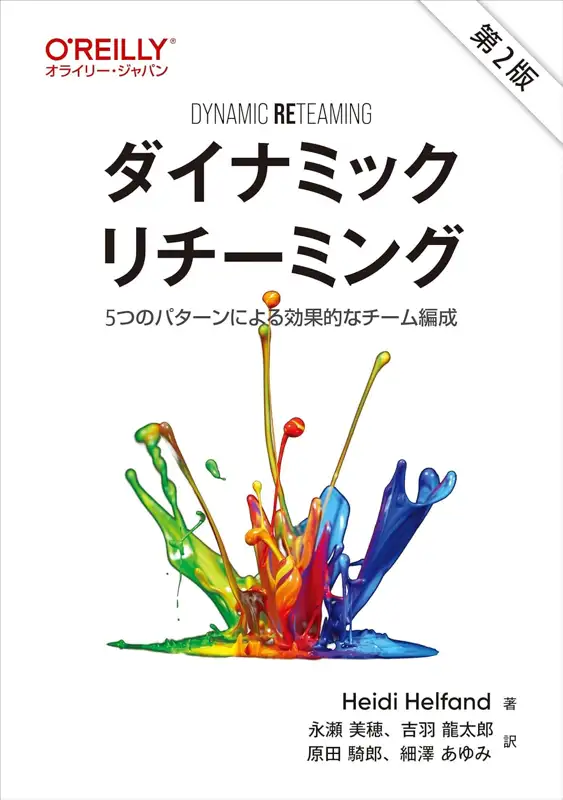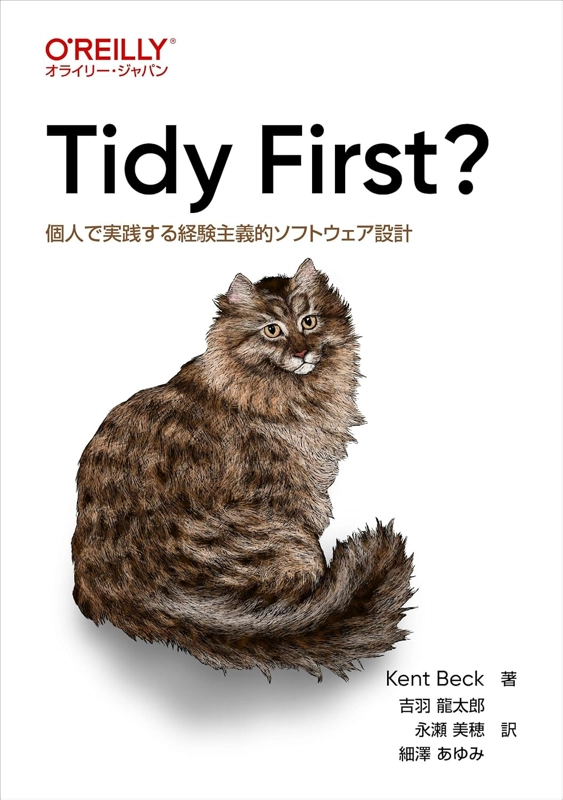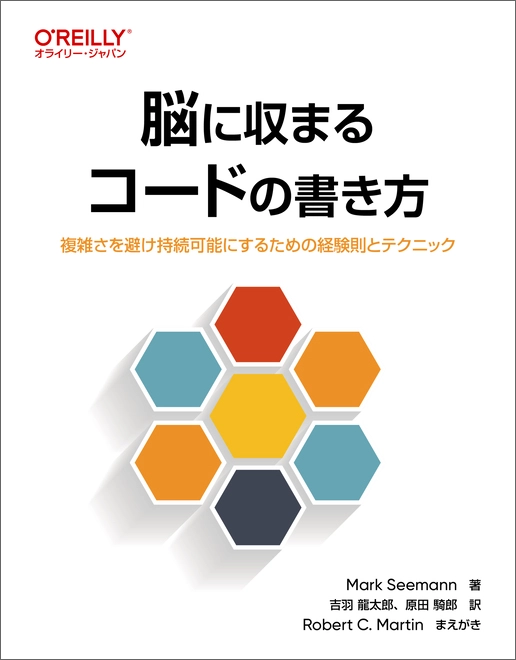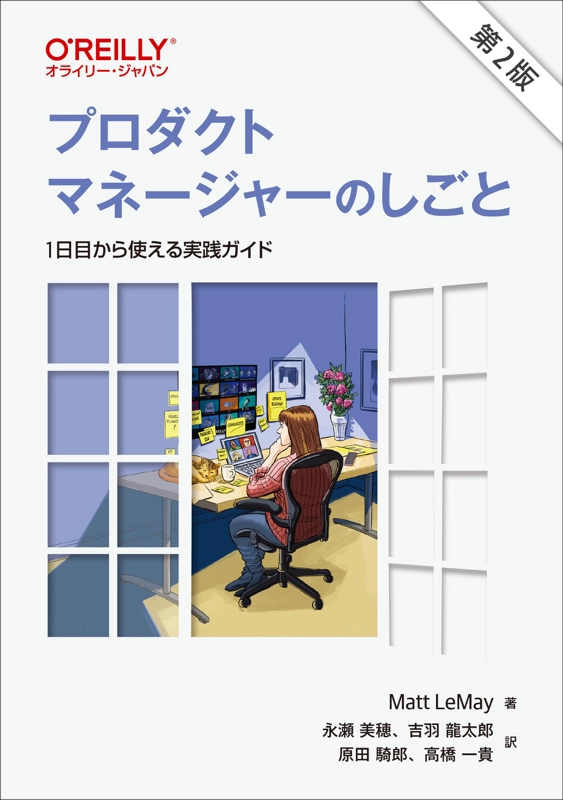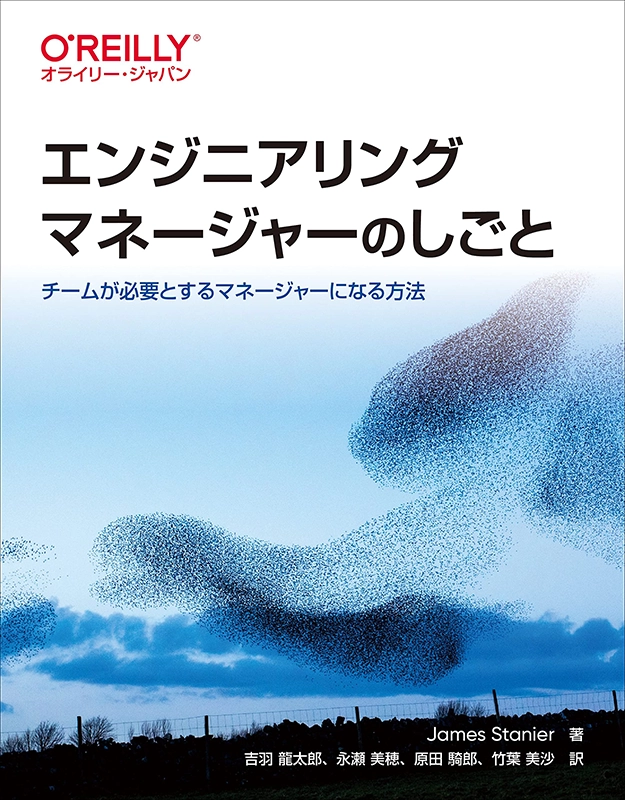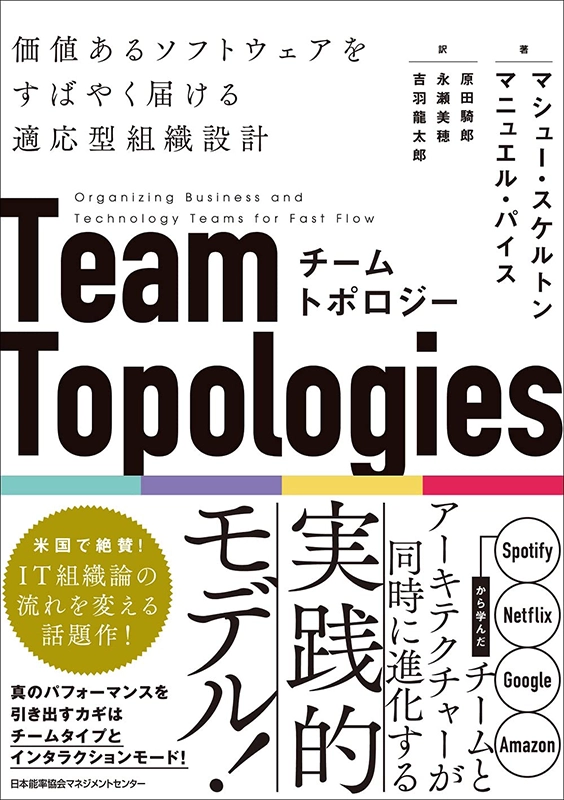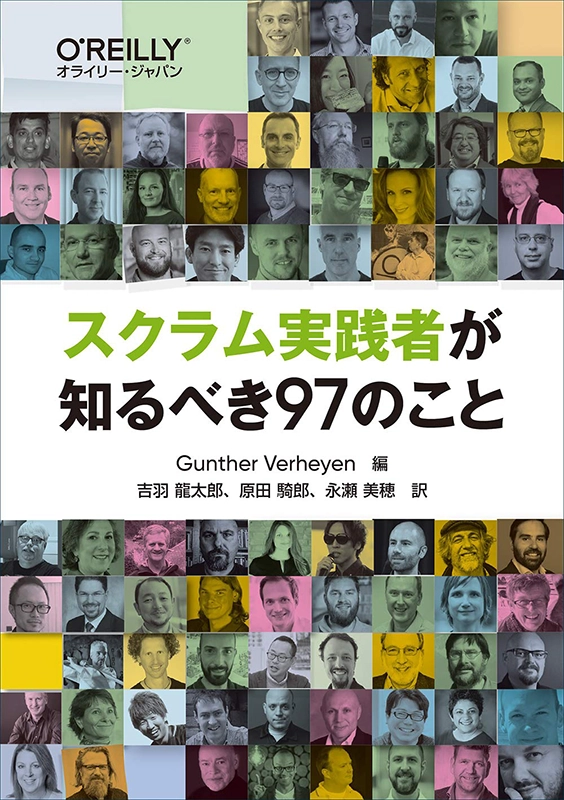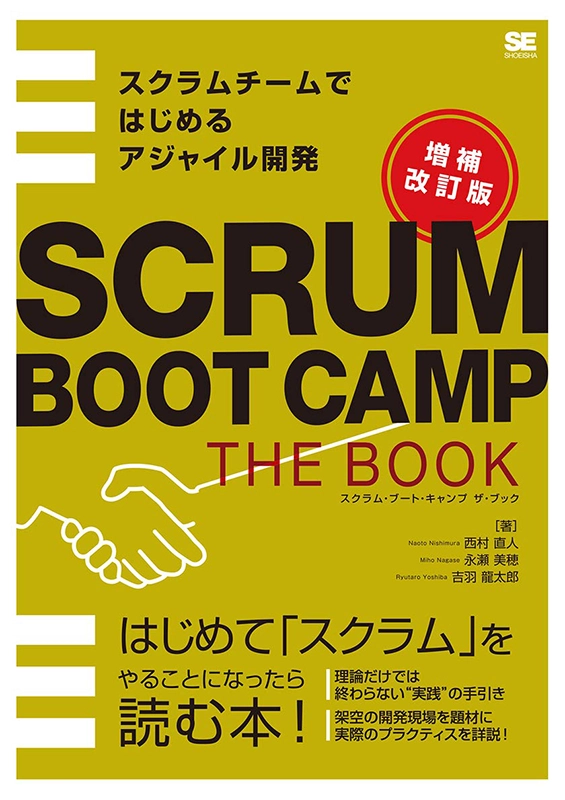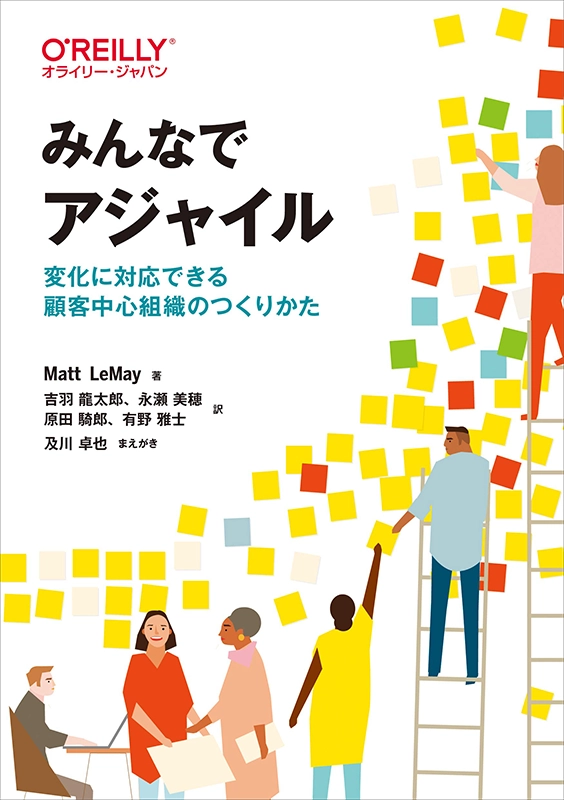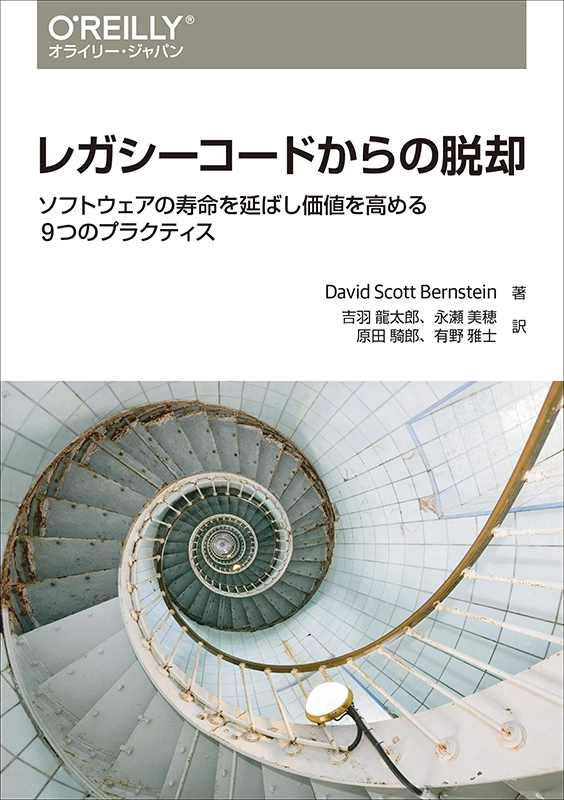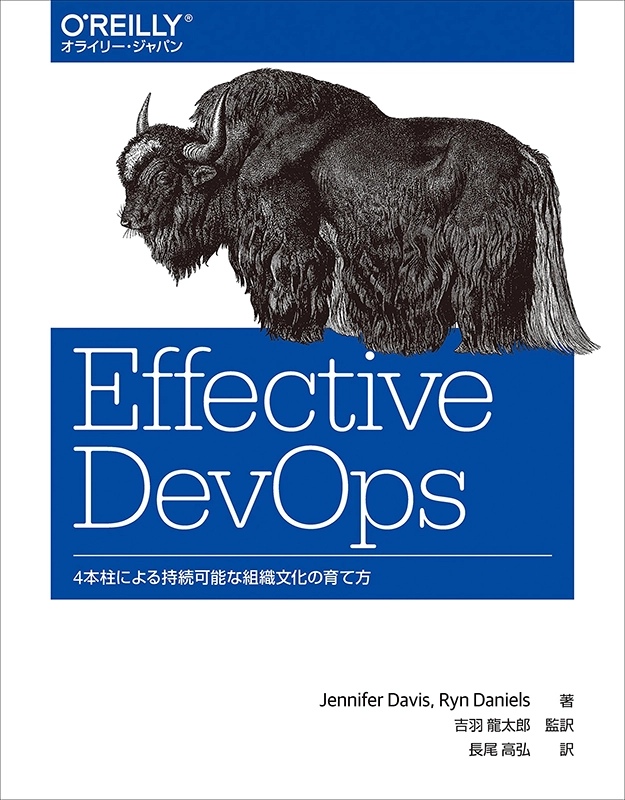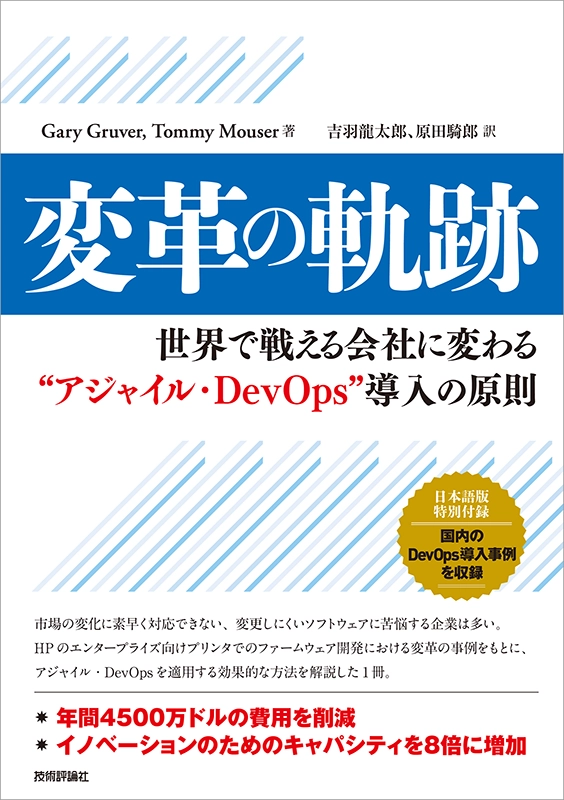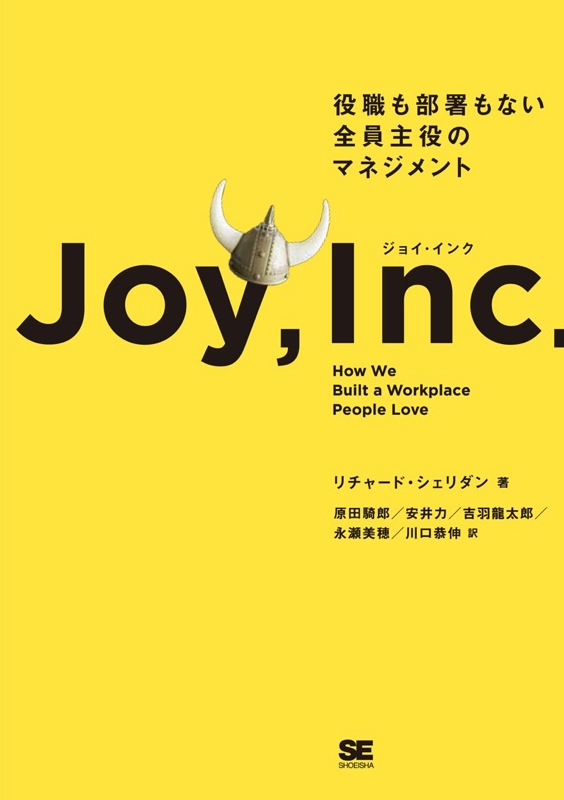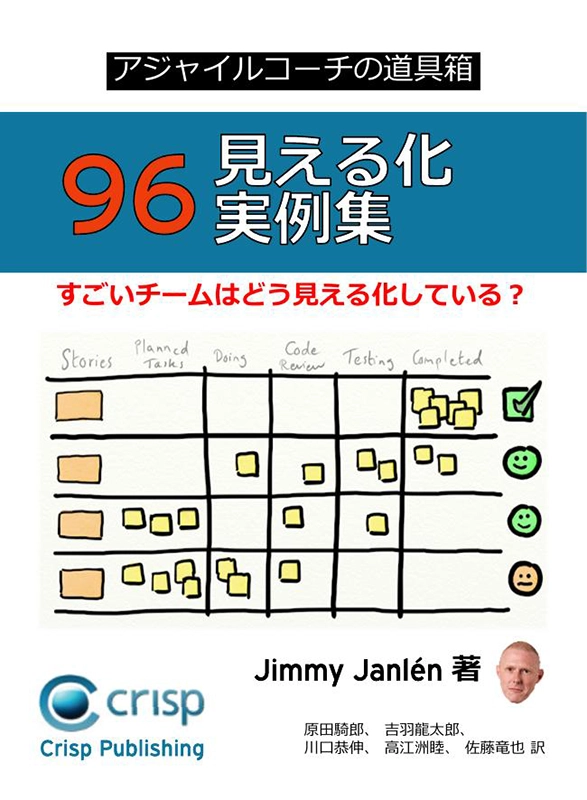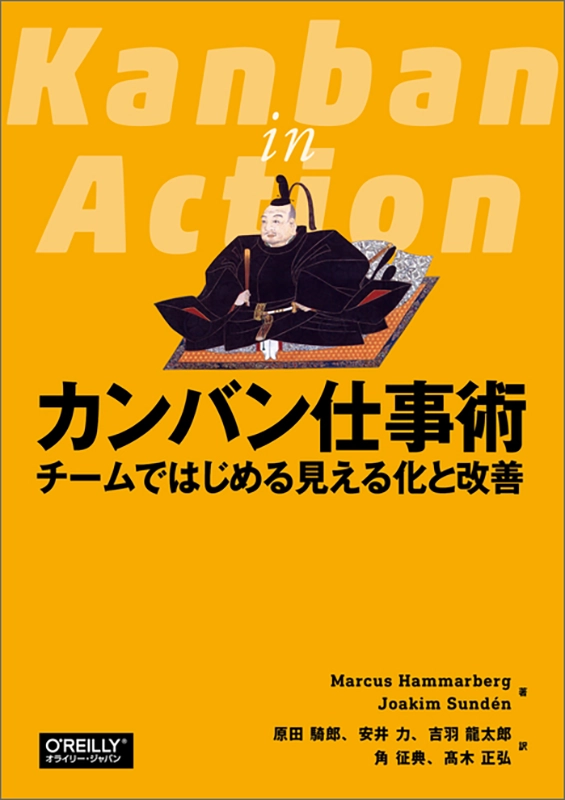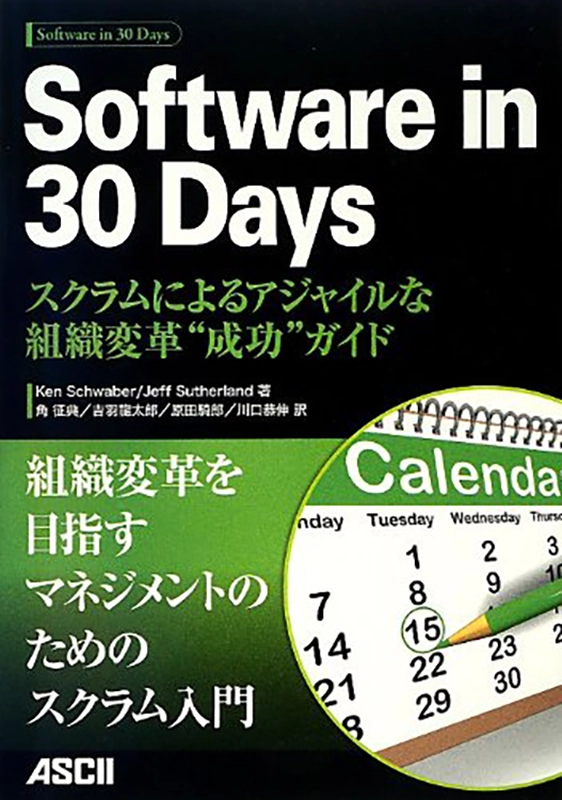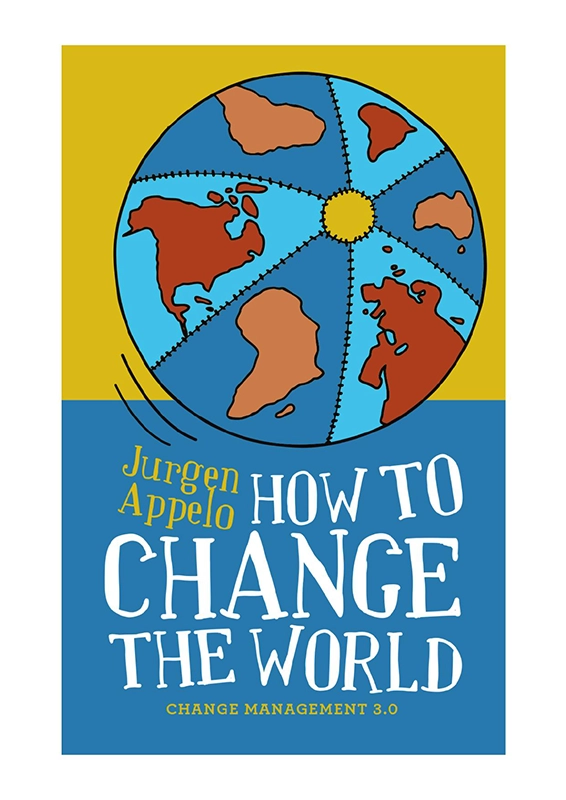直近開催のScrum Alliance認定スクラムマスター研修のご案内
開発者が自分の担当しか気にせず、チームで協力しようとしません。どうしたらよいですか?
スクラムでは、スクラムチーム全体が「毎スプリントごとに価値ある有用なインクリメントを作る」責任を共有し、開発者は「スプリントゴールの達成を確約する」とされています。
にもかかわらず、実際の現場では「自分の担当作業だけを見る」「他の人の作業に関心を持たない」という状況がよく起こります。
その背景には、主に次の3つの構造的な問題があります。
1. 専門分化しすぎている
チーム内で「バックエンド担当」「フロントエンド担当」「インフラ担当」といった形で強く専門が分かれていると、
自然と自分の領域だけを守る文化が生まれます。
これは悪意ではなく、構造的な帰結です。
専門分化が強いチームでは、以下のような現象が起きやすくなります。
- 他の領域の課題にコメントしづらい
- 問題が起きても「それは◯◯さんの領域」となる
- スプリントの途中でボトルネックが発生しても助けに入れない
スクラムガイドでは「スクラムチームは機能横断的である」と明記されています。
これは単に職種が混ざっていることを指すのではなく、協力してどの作業にも着手できる状態を目指す、という意味です。 最初から全員がフルスタックであることを求めるのは難しいですが、徐々にスキルを増やしていく必要があります。
2. スプリント開始時にタスクをまとめてアサインしている
スプリントプランニングの時点で、「この作業はAさん」「こっちはBさん」と割り当てをしてしまうと、
その瞬間にチームの自己管理は奪われます。
誰が何をいつどうやってやるかを決めるのは、スプリントの中で開発者が自分たちで行うべき検査と適応のプロセスです。
事前アサインしてしまうと、以下のような副作用が起こります。
- 「自分の分だけ終わらせればいい」という心理が生まれる
- チーム全体での進捗を気にしなくなる
- デイリースクラムが「進捗報告会」化する(そしてみんな黙って聞いている)
スクラムの本質はスクラムチームによる自己管理です。 スクラムマスターやシニアな開発者などが「仕事を割り振る」形を続けていると、 いつまでもメンバーは受け身のままになります。
スプリント開始時には、誰が何を担当するか決める必要はありません。 進捗や状況に応じてチームが話し合って調整するようにしましょう。
3. スプリントゴールを有効に活用できていない
スプリントゴールが単なるプロダクトバックログアイテムの羅列だったり、スプリントゴールが抽象的すぎたり、そもそもスプリントゴールを設定してはいるもののステークホルダーに何も伝えていなかったりすると、当然ながらスプリントゴールに関心を持たなくなります。 結果的に、向かう方向がはっきりしないので、「自分の作業」ばかりを見てしまうことになります。 このような状況だと、たぶんスプリントレビューもうまく機能しておらず、作業報告会のような意味のないイベントになっています。
スプリントレビューで、スプリントゴールをスクラムチームとして達成できたかどうか、プロダクトゴールに向けた進捗がどうなっているかをステークホルダーに共有してください。 毎回のように「スクラムチームとして意味のあるスプリントゴールを達成できていない」という状況になれば、スクラムチームのメンバー自身が問題に気づくはずです。
スクラムマスターの役割は、「協力しろ」と説教することではなく、チームがそうせざるを得ないように構造を変えることです。
カテゴリ
SCRUM BOOT CAMP THE BOOK【増補改訂版】 スクラムチームではじめるアジャイル開発
- 著者/訳者:西村 直人、 永瀬 美穂、 吉羽 龍太郎
- 出版社:翔泳社
- 発売日:2020-05-20
- 単行本(ソフトカバー):288ページ
- ISBN-13:9784798163680
- ASIN:4798163686